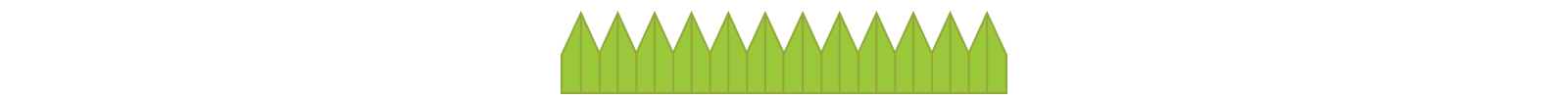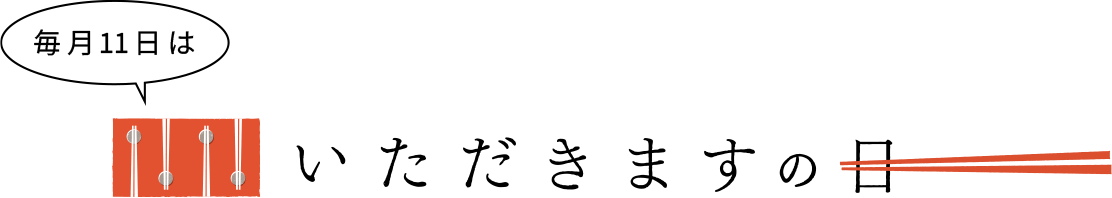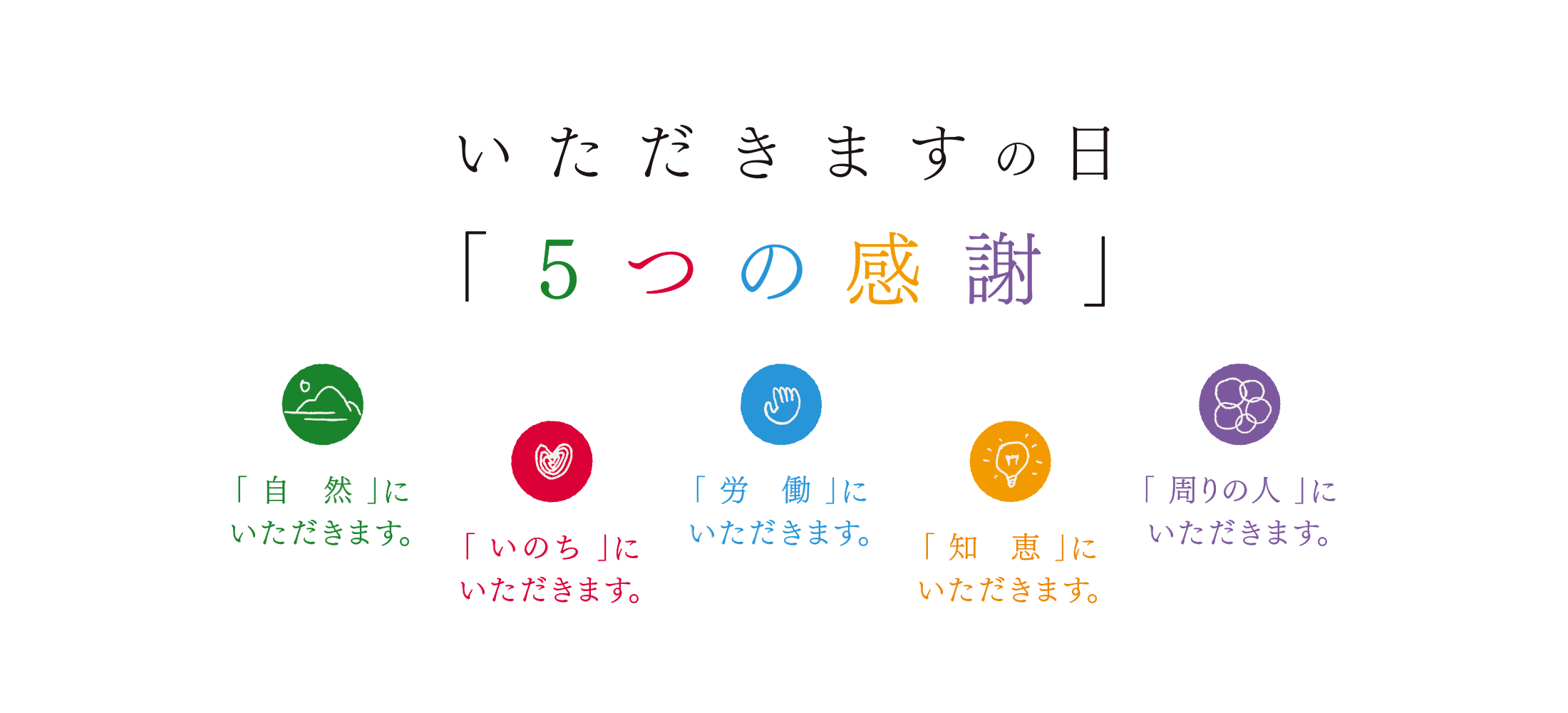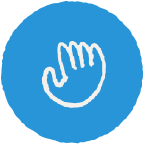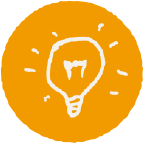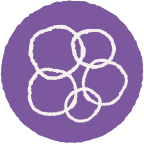おにぎりイベント、参加者募集です!

お米を食べない人が、どんどん増えているそうですよ。農林水産省によると、米の1 人当たりの年間消費量は、昭和37 年度の118kg をピークに減少傾向となっていて、令和2 年度の消費量は半分以下の50.8kg にまで減少しているそうです。食欲の秋、何杯でもおかわりしているよ!という人ばかりじゃないってこと!「いただきますの日」としては、日本食の原点であるお米の消費拡大を応援したい!とうわけで「おにぎりをみんなで作って みんなでいただきますの会」を開催します。第1弾のテーマは「具」。参加者みんなが、とっておきの「具」を持ち寄って味とうんちくをみんなでシェアします。!ぜひご参加ください。
| と き | 2023年11月10日(金)18:00~21:00 |
|---|---|
| ところ |
新渡戸文化学園 家庭科室 |
| 定 員 | 10 名程度 |
| 参加費 |
2,000 円 ※当日お釣りが出ないようにお願いします。 |
| お申込 | イベント終了しました。 |
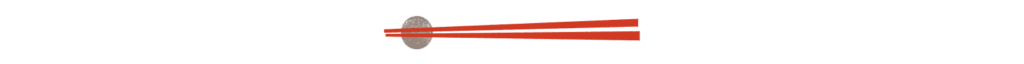
当日のスケジュール
1)まずは炊飯
2)炊けるまで おにぎりプレゼン!
・おにぎり歴史 ・地域のおにぎり ・おいしい握り方 など3)実食